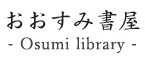ブログ・エッセイ
大聖寺藩、一庭啓二、石川嶂、市橋波江、パトロン事件、実性院、「義心院善翁道器居士」、あいの風とやま鉄道
このお盆(2018年8月)、所用があり富山に三泊した。
往路は、まだジパングが使える8月10日だったので、快速と普通を乗り継いで北陸本線の大聖寺で降りて街を少し歩いた。
大聖寺は、いま伝記を書いている一庭啓二(琵琶湖蒸気船一番丸船長)と共に長崎に赴いた石川嶂の出身地である。石川と一庭は長崎で蒸気機関を買いつけ、大津に戻ってそれを組み立て、初めて琵琶湖で蒸気船を浮かべた人物である。大聖寺の駅を降りると駅前には、「加賀江沼人物百選」という大きな看板が掲げられていて、石川嶂もそのひとりに選ばれている。
今回大聖寺で降りたのは、明治維新期、大聖寺藩士で資金調達のため贋金造りを行ったとされて切腹となった市橋波江の墓所に詣でたいと思ったからであった。この贋金造り、通常パトロン事件といわれるが、この偽金を造った城山のふもとの洞窟にもいってみたいと思ったからだった。なお市橋もこの「加賀江沼人物百選」に名を連ねている。
パトロン事件であるが、これは明治2年夏、藩の貨幣偽造が発覚して重臣らが処分された事件である。発覚というが、こうした偽造は、当時他藩でも行われていたことでもあった。ただ、加賀藩の支藩で小藩の大聖寺藩が、琵琶湖に蒸気船を浮べたり、また小梅といわれた偽造貨幣がたいそうよくできていたりしたことから、他藩がやっかんで讒言(ざんげん)したのだともいわれる。
この「発覚」した贋金造りでは先の石川嶂が、その処分というか処理というか解決のために動いている。石川は、弾正台大忠の海江田信義とも知り合いであったが、このように京阪地域に広く人脈を持っていたからである。
石川らはその事件解決のため、藩の幾人かの重臣や藩の御用商人らを処分したうえで、当時藩の武具奉行であった市橋波江に責任を負わせて、文字通り詰め腹を切らせて切腹させ、この事件を収めたのであった。明治2年6月のことである。市橋波江はこの時五七歳。藩は波江の死後、子の誠市郎に対し、三四〇石に加増して報いた。
この市橋波江の墓所は、大聖寺の寺町とでもいうべき寺院が立ち並ぶ通りの西の端にある曹洞宗の実性院に葬られていた。実性院は大聖寺前田家の菩提寺でもあり裏山の奥に歴代藩主の墓所も立ち並んでいる。
市橋波江の墓所は、藩主の墓所への登り路、その途上に三基ならんであった。波江の墓所と思われるのは左に建つもので、募面は、「明治巳己六月七日」「義心院善翁道器居士」と読める。明治巳己年は明治二年なので間違いないかと思う。
波江は金工細工に秀でていて、市橋の屋敷跡からは箪笥引手金具の鋳型などが出土し、自邸で金工細工の内職などをしていたとされる。この戒名も、金工細工に優れていたということからつけられたものなのであろう。
帰路、加賀市立図書館に立ち寄って、江沼人名事典などコピーさせてもらった。その後大聖寺の駅に向かい、JR北陸線と、新幹線開業で別会社となった「あいの風とやま鉄道」などを乗り継いで富山に向かった。
この富山地域の、JRを離れての別会社設立は、鉄道ファンにはすこぶる不評だという。確かに不便で交通費もかさむ。それに大阪からの特急サンダーバードがすべて金沢止めで、あとは新幹線に乗り継ぐようにと時刻表が改定されている。暴力的とも言いたいぐらいで、まったく腹立たしい限りではある。(2018年8月19日 記)
- 次の記事 : 吉村昭、『冬の鷹』、前野良沢、慶安寺、墓所、
- 前の記事 : 資料調査、愛知学泉大学、名古屋商工会議所、大阪市立大学、資料の共有資源化