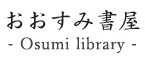ブログ・エッセイ
満洲慰問団、満洲演芸協会、坂野比呂志、後藤資公、黒木曜子、中島敬冶、坪井與、花柳緑(中島市蔵)、久保春国、小林春雄、小林定義、小西明憲、高田常次、藤川公成、中山義雄、許斐氏利、滝節子、南里文雄、ペロケ舞踏場、美天勝一座、益田隆、斎田愛子、比佐丸、ラッパ、秋田実、荒川芳夫・千枝子、斎田愛子
先に、漫才師で大道芸人でもある坂野比呂志(凡児)の三度にわたる外地慰問について書いた。そこに、交友関係の広かった坂野の周辺の、新京やその他の地域でともに活動した人物の名前を挙げておいた。まだまだ調べ途上ではあるが、ここでは、これら人物について、知ることのできたことがらや、満洲慰問のこと、終戦時の活動について述べておきたい。
1 坂野比呂志が昭和9年10月に渡満した時の新京会館の関係者
〈後藤資公〉…バンドマスターでアコーディオン演奏家。戦後も活動していたのだが、昭和34(1959)年2月18日、妻の黒木曜子と娘とを町田市自宅付近の小田急線踏切での事故により亡くした。後藤はその二か月後に、事故現場の踏切で服毒自死した。妻の黒木曜子は本名井関ふさ子、大正10年大阪の生まれ。黒木も渡満していて、戦後に引き揚げたのちはコロンビアレコードに所属し、「ベサメ・ムーチョ」などヒットを飛ばした。作詞も手がける。黒木曜子の墓所は大阪市大正区三軒家東の了照寺で、ここに母子ともに祀られている。
〈中島敬冶〉…新京日日新聞記者
〈野中進一郎〉…大新京日報記者。野中については、子息野中雄介がそのホームページで、野中進一郎の詳細な伝「日中戦争時代の父・野中進一郎」を書いている。ここに書かれてある「当時の遊び仲間」を次に引用させていただく。
「当時の遊び仲間は、久保春雄(横浜市商工新聞社主幹)、藤川公成(満映勤務。教育テレビの元プロデューサー)、花柳一蔵(本名・中島一蔵、映画館の館主)、小西明憲(故人。金物タイムス主幹。私の妹の夫が氏の次男)、坂野比呂志(漫談家、ガマの油売りの大道芸で芸術祭大賞を受賞)、中山義夫(ダンサー石井漠の弟子)、高田(ギンザシネマなど新京の映画館で看板を描いていたが本職は画家だった)、坪井(満映のカメラマン)などだった。」(2020年11月8日閲覧)。
〈坪井與〉…野中の「遊び仲間」とされる坪井與は明治42年福岡県の生まれ。東京帝国大学の仏文を卒業後に渡満、満洲日日新聞を経て昭和12年満洲映画協会に入社し昭和18年上映部宣伝課長。監督も務めた。当時満映にいた北村謙次郎『北辺慕情記』には、坪井は製作課員とある。昭和13年に「万里尋母」を監督として撮っている。新京郊外の寛城子にスタジオと宿舎が出来てそちらに移った。坪井は一軒家に住み、椅子テーブルにベッド、電蓄も備えての暮らしであったという(前掲北村謙次郎)。坪井は、昭和13年2月の『満洲映画』に「座談會 吉林ロケーシヨン漫筆」を書き、同号に坪井らの作品「村の英雄」(仮題)の写真も載っている。
なお坪井は『月刊満洲』昭和12年12月に「滿洲映畫俳優採用試驗漫談」を書いている。
戦後は東映取締役(「満洲映画協会の回想『映画史研究』1984年、『満洲紳士録 昭和18年』、野中雄介ホームページ)。
〈花柳緑(本名中島一蔵)〉…吉野町の銀座シネマ支配人兼主任弁士。豊楽劇場支配人を兼ねていた。終戦前には名家荘の観業劇場、北京の飛仙劇場・南苑劇場、太原市柳条溝の太原劇場を経営した。
〈久保春国〉…先の「遊び仲間」の久保春国は、『満洲紳士録 昭和18年』および先のホームページによれば、九州帝大法文学部卒で大新京日報経理部勤務、のち昭和16年3月日満商事資料室弘報課係主任、翌年11月資料室統計係主任。
戦後は横浜で『商店街新聞』を発行していた。著書に『新選人物伝 世界の75人の”ことば”と人間像』商業新聞社 1990年、『先人の言葉のはなし』横浜商工会議所中小企業相談所 1985年。
〈小林春雄〉…野中のホームページによれば同盟通信太原支局記者。戦後は共同通信勤務、共同フォトサービス社長、東京ポスト広告社長。
〈小林定義〉…新京敷島警察保安課長。坂野は昭和12年に小林から満洲国退去を通告されたという。
〈小西明憲〉…北大卒、大新京日報に勤務。『逓信協会雑誌』一九三四年七月号に「遞信事業と探偵小説」を書いている人物か。
〈高田常次〉…城内各所に壁画を描いた「宮廷画家」。
〈藤川公成〉…「新しい文化の創造」を求めて渡満し、図案や看板描きで生計を立てながらラジオ放送をやっていた(坂野の回想)。昭和10年二人は鈴木泉三郎「生きてゐる小平治」を満鉄西倶楽部で上演した。
藤川は昭和20年5月に召集、9月4日、新京駅からにシベリア抑留となった。(「引揚げ者100人の告白『潮』1971年8月、「特別企画 日本人の侵略と引揚げ体験」、兵役およびシベリヤ抑留については『ヘンな兵隊(1)、2』近代ジャーナル出版部 1970年、にまとめられてある」」。戦後は日本教育テレビ(NETテレビ)の映画部長を務めた。
〈中山義夫〉…バレーダンサー・舞踊家。帰化し霧島エリ子と名乗ったロシアのエリアナ・パヴロワの弟子。新京の満洲舞踊学校の校長。
戦後は民俗舞踊研究所を設立して民俗舞踊の普及に努めた。日本舞踊文化協会理事、農民クラブ生活文化普及部講師。『日本のおどり』(日刊スポーツ出版社 昭和53年)の「はしがき」に、「遠い異国にあっても、ふるさとの唄と踊りは、やさしい母の言葉のように私の心をゆさぶり」と書き、昭和のはじめ頃から、各地の民謡の振付をするように」なったと述べている。
〈直塚太郎〉…
〈鬼木某〉…福岡のテキ屋の親分
〈安部某〉…憲兵隊少佐
〈梅香〉…(本名斎藤のい子、のち坂野のい子)…吉野町「新杵」の芸者
〈許斐氏利〉…関東軍特務機関員。なお許斐(このみ)氏利(うじとし)については牧久の詳細な評伝がある(『特務機関長許斐氏利 風淅瀝として流水寒し』(ウェッジ 2010年)。ここでは新京の許斐のことを書く。許斐の大陸行きは昭和12年1月11日、井上磯次と同道であった。まず安東の伊達順之助のもとに行き射撃訓練など指導を受けた。その春に新京の関東軍情報担当第二課参謀田中隆吉のもとへ向かう。ここで待機し満洲の情勢を勉強するようにと言われ、ひとり千円の大金を支給された。この大金で許斐らはダンスホール新京会館で豪遊したのであった。札束を切って傍若無人に遊ぶ許斐は会館で反感を買い、喧嘩を売られる。牧の前著によれば、喧嘩を売ってきたのは六人の中国人とあるが、これが坂野らとの喧嘩であったのかもしれない。坂野の回想では、新京日日の中島敬冶が許斐のゴシップ記事を書いたことから許斐の怒りを買い中島を殴ったこと、その仕返しとして坂野らが喧嘩を仕掛けたのだという。許斐は特務機関で訓練を受けた人物で、のちには天津・上海、仏印などで諜報機関を組織して活動するような、いわば筋金入りであり、そんな許斐に喧嘩を売ったところでかなうわけもなく、坂野は逆にやり込められる。この事件は警察沙汰になり、許斐は新京から遠ざけられる。その後哈爾浜に機密書類を届けるよう言われ、その帰還後には天津での諜報活動を命じられて天津に向かう。このとき坂野は許斐に誘われてともに天津に向かったのだという。許斐と坂野は、天津に行く途中の山海関付近で「匪賊」に襲われ捕まった。九死に一生を得てようやく脱出、雪の中を必死で逃げた。坂野は雪の中で睡魔に襲われるなか、満洲の地で凍死したという田村邦男のことなど思い起こしながら、意識を失い天津の病院に運ばれ、なんとか生き延びた、というのが坂野の回想である。この田村邦男は日大相撲部出身の俳優で、昭和16(1941)年2月山西省で死去した(『都新聞(現・東京新聞)』)。
さて終戦時の許斐であるが、昭和20年4月に上海でアメリカの沖縄上陸作戦を知り、急ぎ福岡に戻り沖縄に向かおうと試みる。若いころ世話になった長勇参謀長が激戦の沖縄にあり、その長と「一緒に死ぬ」と以前に交わした固い約束を守るためであった。しかしながら沖縄に向かう飛行機が悪天候で墜落、重傷のなか生き延びて6月中旬に自宅へ戻り療養、ここで長の自刃を知ることとなったのだという。許斐の生涯については、牧久の労作『特務機関長許斐氏利』を参照されたい。
〈滝節子〉…ダンサー。坂野比呂志はこの滝に誘われるかたちで満洲行きを決めたという。滝は新京から奉天に移ってブロードウエイに出演。このブロードウエイは、満洲当局から最初に許可を得たいわば老舗ダンスホールあった。奉天に移動した滝を追って坂野も奉天へ行くこととなる。
〈南里文雄〉…トランペット奏者。明治43年大阪市久宝寺町に生まれる。父は鴻池銀行員。大正14年に高島屋少年ブラスバンドが出来た時に入隊。ここでは谷口又士・芦田満・中澤濤士らと一緒だった。このバンドは2年後に解散となり神戸の海岸通りKNKダンスホールに移って演奏活動を始める。バイオリン・トロンボーン・トランペット・サキソフォン・ピアノ・ドラムといった編成であった。全国のホールを回った。昭和3年9月東京に出て、関西系の井田一郎「チェリー・ランド・ジャズ・バンド」の第二チェリーランドに属して研鑽を積む。浅草電気館・麻布ダンスホールなどに出演。昭和4年9に上海に渡り、北四川路のアパートに住みながら外国人のバンドを聴く。昭和5年8月コロムビアに招かれ帰国し、10月にコロムビア・スタジオオーケストラに入った。昭和7年3月、秩父丸の船内バンドで渡米し、10月に帰国。東京の溜池のフロリダに出ていた菊池滋彌の率いるバンドに加わった。昭和11年秋になり大連の名門「ペロケ・ダンスホール」からの使いでホールへの出演を懇請される。迷った末に渡満を決意して9月に大連へ。心配していた満洲での生活も思いのほか居心地がよく、ホットペッパーズを率いて大連の名門ダンスホール「ペロケ舞踏場」に出演した(塩澤実信「南里文雄 上中下」『スイングジャーナル』 (27)1950年8月ー10月)。この少し前までの大連では、ダンスホールといえば白系ロシア人が経営する「ビクトリヤ」「ボンベイ」だけだったが、昭和7年には日本人経営のホールにも許可が下り、「ベロケ」「大連会館」「東亜会館」「第七天国」などが開店してダンスホールの一大ブームとなった。このうち連鎖街の近くにあったベロケが一番広くて、ミラーボールの五彩色、華やかな雰囲気で、トランペットの南里を招聘して満員であったという。なお「第七天国」は健康的な雰囲気のダンスホールで、遼東ホテル7階にあったまた大連会館には山下久が出演していた (松原一枝『幻の大連』新潮新書 2008年、『大連のダンスホールの夜』中公文庫 1998年)。
常盤座でのミュージカルショー「ピーナツ・ヴェンダー」の出演も果たした。ところが昭和15年10月にホールは閉鎖となり帰国、松竹軽音楽団に所属して劇場などで演奏するも、いわゆる敵国音楽とされるジャズなどは到底許されるわけもなく軍歌・国民歌謡を演奏するばかりであった。昭和17年にはSKD(松竹歌劇団)のメンバーとフィリピンの慰問にも出かけた。2か月の慰問の旅を終えて帰国、すると今度は生産意欲を高めるためにと編成された吹奏楽団に加えられる。昭和19年5月、日立への慰問時に召集令状を受け、その日のうちに久留米の部隊に入隊した。上官の理不尽な仕打ちに堪え除隊、そして20年7月に再招集されて衛生兵の一等兵として軍務に。山口県七味の病舎で看護に務めるなかここで終戦を迎え9月に復員した(塩澤実信「南里文雄 上中下」『スイングジャーナル』 (27)1950年8月ー10月)。
ところで先の松原一枝『大連のダンスホールの夜』に所収の「大連のパトロンとテロリスト」のなかに、終戦を大連で迎え生活に困窮した日本人が蔵書を売り始めたとき、文学書を中心に、須知善一が盛んに買いあさったという話が出ている。その書物の購入を任されたのは、かつて首相原敬を暗殺した中岡艮一だったという。この須知の買い集めた書物がその後どうなったか興味を惹かれるところだ。後日のためにここにメモをしておく。
2 坂野比呂志の二度目の慰問は朝鮮
〈美天勝一座〉…東京に戻って坂野は美津子と漫才のコンビを組んだが美津子が結核で倒れ、ひとりで司会などをこなしていたところ、この美天勝一座とともに朝鮮から満洲への興業の話が舞い込む。奇術の松旭斎天勝一座をまねて立ち上げた一座。この時の一団は、バンド七人ほどを含め総勢30人。釜山・大邱・京城と公演して満洲に入る予定だったが、京城で一座の中から天然痘患者がでて解散。坂野は特務機関の知り合いがいた天津に向かう。
〈松旭斎天左一座〉…松旭斎天勝の弟子松旭斎天左の一座。天津劇場に出演していた。
3 昭和20年5月の慰問、終戦時の「新京残留慰問団」、引き揚げ
〈古今亭志ん生〉
〈三遊亭円生〉…この二人はすでに述べた。
〈国井紫香〉…活動写真の弁士、講談師。本名饗庭吉之助。のち国井姓。神田伯知(二代目)とも名乗った。明治27年東京本郷の生まれ。文京区京華中学に進むも放校となり逗子開成中学に転校する。明治大学商科に進学したが予科2年修了前に中退し大正2年2月に毎夕新聞社会部記者となる。文芸部には広津和郎もいた。新聞社も数ヶ月で退社する。活動写真弁士川辺紫水、内藤紫漣の弟子となり、各館で無声映画弁士として活動したが有声のトーキーが現れ講談師に転向する。浅草遊楽館など劇場を経営するが経営不振。満映の招きで満洲に渡る。
昭和22年に引き揚げた。学昭和41年4月26日に亡くなった。自伝に『駄々ッ子人生』 妙義出版 1956年。
〈荒川芳夫・千枝子〉…漫才
〈秋田実〉…明治38年に大阪市東区玉造で生まれる。本名は林廣次。父親は砲兵工廠の鋳物職工であった。旧制今宮中学から大阪高校、東京帝大文学部支那哲学科に進学。新人会に参加しまた雑誌『大学左派』、『戦旗』の編輯にもかかわる。在学中から執筆活動をおこない、昭和6年12月、朝日新聞記者白石凡と旧友の藤沢恒夫とともに寄席の横山エンタツ、花菱アチャコらと会った。昭和7年大学を中退か。昭和10年吉本興行に入社し漫才台本を書く。昭和13年10月『皇軍慰問 爆笑漫才熱演集』を刊行、以後続刊。この年の1月には吉本興業・朝日新聞の共同で第一回「わらわし隊」が東京を出発。昭和15年春、大宅壮一と満洲旅行に出かける。娘の藤田富美恵の回想によれば、大宅は不意に家を訪ねてきて、あすの汽車で満洲に出発しよう、切符は用意してあると言った。新京に着いて大宅は、今から一週間、ひとりでどこに行ってもよい、一週間目の午後6時に新京放送局で落ち合って二人で対談をすると言われたのだという。秋田は哈爾浜など方々の都市を巡覧した。この渡満は、5月29日満映傘下の満洲演芸協会の発足のためのものかと。昭和16年10月吉本興業から新興キネマ演芸部に移籍。昭和20年3月9日、満洲映画協会演芸部員として渡満、満洲演芸団の組織化を依頼される。十ほどの劇団を結成した各地を巡演しようとしていた矢先に新京で終戦を迎える。昭和21年10月満洲を出て11月1日引き揚げ、博多に上陸して福井で家族と再会した。11月末、秋田は房江夫人と子どもと京都の房江の実家に移った(浦和男「秋田實年譜」『大阪春秋』2018年秋号、藤田富美恵『父の背中』潮出版 1989年 など)。
〈浜田リナ・リサ〉…
〈泉けい子〉…
〈二村定一〉…
〈益田隆〉…明治43年東京の生まれ。昭和3年松竹に入社、発足したOSK(松竹歌劇団)の運営に関わる。昭和10年松竹を辞めて東宝へ。東宝舞踊隊と改称されたNDK(日劇ダンシングチーム)を率いて昭和一五年九月、東宝舞踊隊副団長として満洲ほか中国大陸各地を慰問で巡回。終戦直後は新京に残り、オペラ歌手斉田愛子らと駐留軍を慰問、昭和二一年一一月に帰国している(西浦義夫「益田隆研究 日本洋舞史の一側面」『舞踊學』第五号 一九八二年)。
〈斎田愛子〉…歌謡曲「長崎物語」のレコードも出しているアルトのオペラ歌手。本名橘良江、明治43年カナダの生まれ。昭和6年にトロント・コンソルバトーリを卒業。昭和10年に日本で歌手デビュー、藤原歌劇団でオペラに出演した。また昭和18年には「戦友の遺骨を抱いて」の吹込みもおこなっている。
この歌の誕生は次の通りだった。昭和17年2月、日本軍は多くの戦死者を出してシンガポールを陥落させたのだが、その入城のおりにおびただしい遺骨を肩にして兵士が行進した。その兵士のうちのひとりに近衛師団経理部所属主計軍曹逵原実(つじはら みのる)もいた。逵井も忘れられぬ戦友の遺骨を飯盒に入れて行進したのであった。逵原はこの戦友のことを思い、「戦友の遺骨を抱いて」の詞を書いた。それを報道班の長屋操に渡し、報道班編輯の陣中新聞『建設戦』昭和17年2月24日に載ったのである。このとき、詩に曲をつけた投稿が10通ほどきたが少し曲調が合わず、その後にやってきた海軍軍楽隊に依頼してあらためて作曲をしてもらった。軍楽隊は二曲提出したが、シンガポールの各地の慰問では、その一曲の松井孝造作曲の同歌がよく唄われた。
当初は現地のマレーシア人ら二人に歌唱指導をして歌わせたが、7月に日本から斎田愛子や石井亀次郎が慰問団(南方皇軍慰問芸術団)としてやってきて、斎田や石井が歌い、また舞踊家の江口隆哉が振り付けて踊ったりした。南方皇軍慰問芸術団が歌った歌は、日本に持ち帰られ、軍楽隊の提出したもう一曲もふくめてレコ―ディングがおこなわれ、酒井弘、鳴海信輔・斎田愛子、石井亀次郎、東海林太郎らが歌って吹き込みをしている(逵原実 長屋操 松井孝造「戦友の遺骨を抱いて」『新編私の昭和史 2 (軍靴とどろく時)』東京12チャンネル社会教養部編 学芸書院 1974年、長田暁二『昭和歌謡 流行歌からみえてくる昭和の世相』敬文舎 2017年など)。斎田はその後に満洲の慰問に出かけて、終戦となり新京に残されたということなのであろう。
ちなみにこの時期、「シンガポール晴れの入城」という歌が、野村俊夫作詞 古関裕而作曲で作られている。この野村も古関もNHK朝の連続ドラマ「エール」のモデルとして取り上げられた。
〈上野耐史〉…
〈平和ラッパ・日佐丸(初代)〉…日佐丸は発疹チフスで亡くなる。
〈金尾仁三郎〉…福岡の出身。博打打ちの一家を立てようと渡満したといい、坂野に劇場上演を勧め、太子堂を改造して舞台をつくったと坂野は述べる。
文字通りメモになったが、分かったことを順次ここに書き加えてまいりたい。
2020年12月20日 記